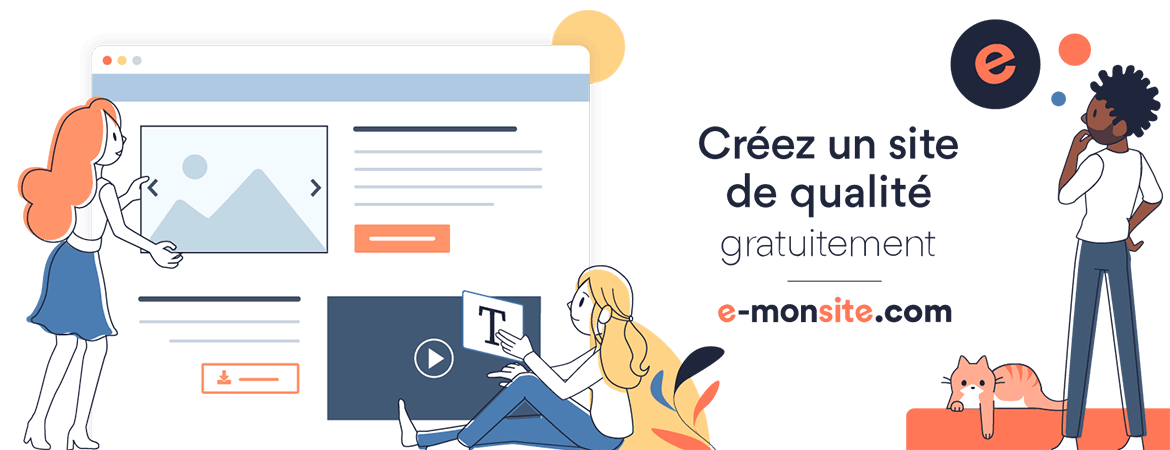「左様に褒め殺しにされたのでは、さすがの儂も立つ瀬がないのう」
「殿…」
「さすがは、わざわざ民の扮装までして、儂の行動を監視し続けただけのことはある」
「本当に大変でございました。殿があちらこちらに行かれるので、私など付いて行くだけで──…」
話す濃姫の顔面が、途端に驚きと焦りに満ちた。
信長の口元にも冷笑が広がる。
「…気が付いておられたのですか…!?」植髮
「女共が三人も、木や茂みに隠れてごそごぞ動いておれば、誰でも気付くわ。
あれで隠れた気になっておるのじゃから、ほんにおめでたい者共よ」
「き、気付いておられたのなら、お声をかけて下されば良かったではありませぬか!」
「馬鹿を申すな。美濃の蝮の娘が町民の格好をして、ひぃひぃ言いながら儂の後を追いかけて来るのじゃぞ?
左様に面白い見せ物、最後まで見届けずして如何する」
「何と意地の悪い…っ」
濃姫は朱に染った顔を、ぷいっと背けた。
我ながら上手く身を隠せていたと自信満々であったのに、とっくに気付かれていたとは…。
姫は恥ずかしくて、まともに夫の顔が見られなかった。
「そう剥(むく)れるな。儂も楽しませてもろうたし、そなたの熱意も一応は伝わって参ったぞ」
「一応、ですか」
「大いに伝わったと申せば満足なのか?」
「そうではございませぬが…」
濃姫は小さくかぶりを振ると、ふいにハッとなって信長を見やった。
「堤防…。殿が私を堤防へと誘われたのは、そのことをご存じだったからなのですね !?」
「今更気付いたのか──。応よ、遠目からではなく、もっと近いところで儂の働きっぷりを見せてやろうと思うてな。
おかげで儂を知る良い勉強になったであろう?」
「ま、何というお方」
「ははははっ」
一本取ってやったとばかりに愉しげに笑う信長に、濃姫はそれ以上何も言い返せなかった。
思わず悔しさが込み上げてきたが、それでも濃姫の心は、信長に対する感心の方が強かった。
『 やはり殿の方が私などよりも一枚も二枚も上手。……じゃが、そうでなければ面白くない 』
濃姫の目が獲物を狙う隼のように鋭く光った。
「はははっ」と、やや仰け反りながら笑い続ける信長が、ふいに身体を前に起こした時
「……何の真似じゃ?」
信長は笑うのを止め、瞬間的に表情を固くした。
今まさに濃姫が、道三から与えられたあの短刀を鞘から引き抜いて、
冷たく光るその切っ先を、信長の目の前に突き付けているところだった。
濃姫は白く細い腕を必死に伸ばしながら、強い眼光で信長を見据えている。
「初の褥の席で、殿はこうも仰いました。“やり手の蝮殿のこと、大方そちに儂を殺めるよう吹き込んでいるのであろう”と」
「……」
「それに答えを出すのだとしたら、ええ、仰る通りでございます。
これは、その為に父上様から頂戴致した御刀。信長という男が真のうつけであった時は、刺し殺せと」
信長は向けられている短刀をチラと見ると
「…それで、この刀で儂を刺すつもりなのか?」
射抜くような眼で濃姫の真面目顔を見た。
すると姫は和やかな微笑を浮かべて、スッと短刀を握るその手を膝の上へ下ろした。
「いいえ。殿がうつけでないと分かった今、私にはもう、あなた様を殺める理由はありませぬ」
刀を鞘に収めると、濃姫はそれを両の掌の上で固く握り締めた。
「それにこれは、私の守り刀でもあるのです。父上様から頂いた大切な御刀……出来るならば、血で汚(けが)しとうはございませぬ」
そう真摯に語る濃姫を見つめながら
「じゃが、刀という物はすべからく何かを斬るために作られた物じゃ。使わねば意味がなかろう」
宝の持ち腐れだと信長は言った。
「確かにそうやもしれませぬ…。なれど、刀を持つ者によって、その使い道も違(ちご)うてくるのではありませぬか?」