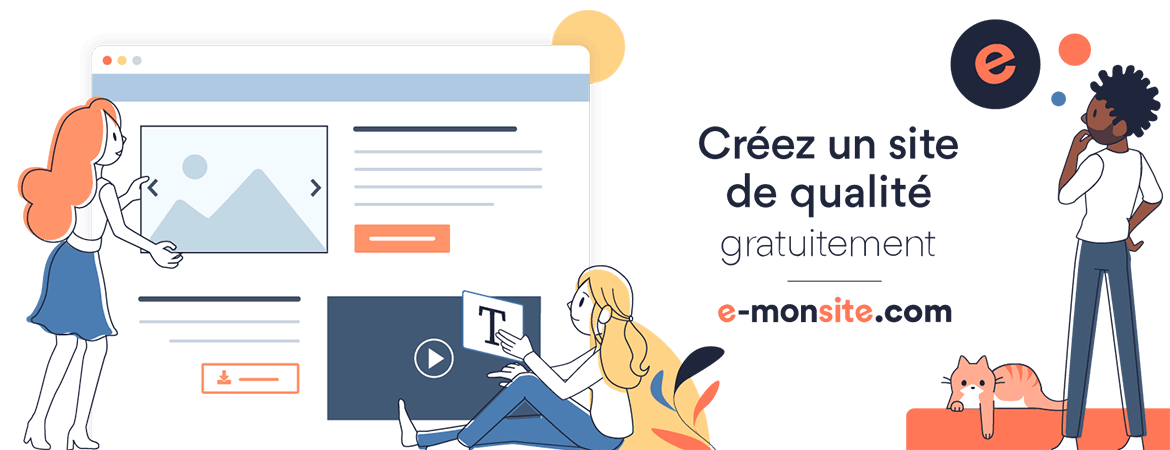だが、それらを祀る建築物には魅せられていた。
それを生み出す工匠たちには尊敬の念さえ抱いていた。
都にはこの地とは比較にならぬほど素晴らしい寺社や塔があるという。
天井の上や床下に入り込んで引手、継手、積み上げ構造と言われる手法をこの目で見たい。
そして、出来ることなら自分の手で造ってみたい、とさえ思った。女房を下がらせ、忠信自ら蔀戸を上げる。
床に座ると庭からホオジロのさえずりが聞こえてきた。
池の畔の木々も岸辺の草むらも色づいている。
「それは、なぜなのですか?」【生髮方法】生髮洗頭水效用&評價! @ 香港脫髮研社 :: 痞客邦 ::
ささらが姫の問いに忠信は頭を下げた。
声は抑えられていたが姫の怒りが伝わってくる。
忠信は、すっかりと白くなった頭をあげた。
齢が五十を超えたあたりから頬がこけ、たくわえた髭も白くなってきた。
「料理を口にする前に鳥や魚についばませているのは……」
「それがなにを意味しているかは、訊かずともわかります。わからないのは、なぜ、そのような用心をしなければならないのかということです。あの者は、それほどの罪を犯したのですか?」
常であれば、人の話をさえぎる姫ではない。
怒りのほどが察せられた。
「イダテンは何ひとつ罪を犯してはおりません。常に、宗我部の手の者が仕掛け、それを避けるのみ。ゆえに用心深くなっているのでしょう……もとはといえば国親がイダテンの母に袖にされての逆恨み」
「……にもかかわらず、誰ひとり手を差し伸べようとしないのは、なぜですか?」
姫の率直な疑問に忠信は言葉を失った。
理由は単純である。
鬼の子だからだ。
宗我部が怖ろしいからだ。
手を差し伸べようものなら間違いなくその人間に災いが降りかかるからだ。
だが、姫に、そう答えることは出来ない。
その責が誰にあるかを気づくだろう。
賢い姫である――あるいは気がついて言っているのか。
額に浮かんだ汗をぬぐうこともできず、老いた頭で懸命に言い訳を考えた。雀のさえずりが聞こえてくる。
空も明るくなった。
「そういうわけにはいきませんよ。姫様にお会いするのですよ」
三郎の母、ヨシが、まなじりを吊り上げた。
イダテンが邸に招かれたといって張り切っているのだ。
早く衣を着替えろと。
正しくは呼び出されたというべきだろう。
気は進まないが、助けてもらった以上、礼は言わねばならない。
それに、出向けば、寝殿造りの邸を、間近に、加えて内部からも見ることができる。
このような機会は二度と巡ってこないだろう。
用意されていたのは、限りなく黒に近い深紫の地に浅紫色の藤の紋をあしらった衣だった。
袍(ほう)と言う名の装束だという。
光沢のある滑るような生地や綾織とやらに驚いた。
これが絹というものか。
麻の衣でさえ父の衣を仕立て直した二枚しか持っていない。
烏帽子も用意されていたが、イダテンの髪は収まりきらなかった。
髪は、黒い布を幾重にも巻いて、つむじの上で束ねた。
束ねた髪は大きく広がり、肩に背中に滝のように流れ落ちた。
土手側の半蔀(はじとみ)から入り込んだ朝の柔らかな光が真紅の髪に降り注ぐ。
髪は、透きとおるように輝き、黒い衣との対比を一層鮮やかにした。「いくら生地が上等でも、童に黒い装束は似合わないと思っていたけれど……姫様の見立てはたいしたものだねえ」
着付けを終えたヨシは、われながら良い出来だと、満足げにため息をついた。
「イダテン、きれい」
ミコは興奮した様子で、イダテンの周囲をぐるぐると回っている。
三郎も、ミコに落ちつけ、と言いながら顔を上気させ、落ちつきがない。
「おお、とてもこの世のものとは思えぬぞ……いいあんばいに、糊がきいておるのう」
「笏(しゃく)や太刀は無理だとしても、檜扇は持たせたいねえ……ちょっと借りてきましょうね」
ヨシは幾度もうなずきながら、家を出て行った。
「ねえ、ねえ、イダテン、姫さまと会うの? だったら、ミコも行きたい。姫さま、いいにおいするの」
ミコがイダテンに問いかけてきた。
そういうわけにもいくまいとは思うが、イダテンに答えられるはずもない。